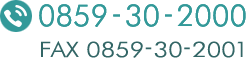お知らせ
月経周期と片頭痛の関係について
2025.10.20
概論と有病率
片頭痛は女性に多く見られる主要な神経疾患であり、その有病率は男性の3倍に達します。女性の生涯において、片頭痛の臨床パターンは生殖期の節目と関連しており、生殖可能年齢期にピークを迎え、高齢者になると減少します。
一般人口の女性片頭痛患者のうち、18%から25%が月経に関連した頭痛を呈します。月経周期は片頭痛のトリガー(誘因)の一つであり、発作の頻度は月経周期によって変動することが示されています。
月経関連片頭痛の分類と特徴
国際頭痛分類第3版(ICHD-3)の付録では、月経関連の片頭痛の診断基準が定義されています。
- 純粋月経時片頭痛(PMM: Pure Menstrual Migraine): 月経周期の月経周辺期(-2日から+3日)に発生するもの。
- 月経関連片頭痛(MRM: Menstrual-Related Migraine): 月経周辺期と、月経周期のその他の時期の両方で発生するもの。
月経に関連する片頭痛発作は、非月経時の発作と比較して、より重度で、消耗性が高く、急性期治療薬に対する反応が乏しい傾向があります。
ホルモンの役割と病態生理
月経周期と片頭痛発作の開始との関連は、主にエストロゲンの変動、特にその離脱効果によって支持されています。
- エストロゲンレベルの低下(離脱):
- 片頭痛発作は、黄体期後期(月経前)のエストロゲンレベルの低下と関連することが示されています。
- エストラジオール(E2)の循環レベルが45~50 pg/mLを下回ると、片頭痛が特に誘発されやすいという閾値が特定されています。
- エストロゲン離脱は、前兆を伴わない片頭痛(MO)と関連しています。
- 黄体期後期の低エストロゲン・低プロゲステロン状態は、オピオイドシステムの中枢神経作用の低下と関連し、その結果、疼痛感受性が高まる可能性があります。
- エストロゲンレベルの上昇(高レベル):
- エストロゲン高レベルの状態(例:妊娠中や外因性ホルモン使用時)は、興奮性神経伝達物質であるグルタミン酸作動系を増強し、皮質拡延性抑制(CSD)の感受性を高めることが示されています。CSDは片頭痛前兆の特徴であるため、高エストロゲン状態は前兆を伴う片頭痛(MA)のリスク増加に関連する可能性があります。
- 対照的に、月経周辺期の片頭痛発作はエストロゲンの離脱により、前兆を伴う可能性が低いかもしれません。
- 神経ペプチドとの関連:
- エストロゲンは、片頭痛の病態生理に重要な役割を果たす感覚神経ペプチドであるカルシトニン遺伝子関連ペプチド(CGRP)の放出を調節している可能性があります。