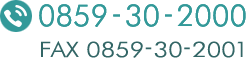お知らせ
2025.06.12
通所リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーション
さくま内科・脳神経内科クリニック通所リハビリテーション事業所運営規程
(事業の目的)
第1条
医療法人聡智会が開設するさくま内科・脳神経内科クリニック(以下「事業所」という)が行う、指定通所リハビリテーション及び指定介護予防通所リハビリテーション(以下「通所リハビリテーション等」という)の適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の従業者が、計画的な医学的管理を行っている医師の指示に基づき、要介護状態(介護予防通所リハビリテーションに当たっては要支援状態)と認定された利用者(以下「利用者」という)に対し、介護保険法の趣旨に従って通所リハビリテーション等を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条
1.当事業所は、通所リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーション計画に基づいて、理学療法及びその他必要なリハビリテーションを行い、利用者の心身の機能の維持向上を図り、利用者が可能な限りその居宅において自立した日常生活を営むことができるよう、在宅ケアの支援に努めるものとする。
2.通所リハビリテーション等の実施に当たっては、利用者の要介護状態の軽減もしくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するようその目的を設定し、その目的に沿ったリハビリテーションを計画的に行う。
3.通所リハビリテーション等の実施に当たっては、関係市町村、地域包括センター、居宅介護支援事業所、地域の保健・医療・福祉サービスとの密接な連携を図り、利用者が地域において総合的サービス提供を受けることができるよう努めるものとする。
4.サービス提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又は家族に対して療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行うとともに利用者の同意を得て実施するよう努めるものとする。
(事業所の名称等)
第3条
事業所の名称及び所在地は以下のとおりとする。
|
名称 |
さくま内科・脳神経内科クリニック |
|
所在地 |
鳥取県米子市長砂町 59-1 |
|
電話番号 |
0859-30-2000 |
|
FAX番号 |
0859-30-2001 |
|
介護保険指定番号 |
3110213521 |
(従業者の職種、員数及び職務の内容)
第4条
事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。
1.医師(管理者含む) 1名
管理者は事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う。
2.理学療法士 3名
通所リハビリテーション等の提供に当たる。
(営業日及び営業時間)
第5条
事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
|
月曜日~土曜日 |
月曜~金曜 9時00分~19時00分 土曜(午前) 9時00分~12時00分 |
|
休日 |
土曜(午後)、日曜、祝日、年ごとに定める盆休み、年末年始 |
サービス提供日及び時間は、次のとおりとする。
|
月曜日~金曜日 (水曜午前は提供なし) |
①9時00分~10時05分、②10時30分~11時35分 |
|
③16時10分~17時15分 |
|
|
土曜日(午前) |
①9時00分~10時05分、②10時30分~11時35分 |
(通所リハビリテーションの利用定員)
第6条
1単位あたりの利用定員は次のとおりとする。 1単位・・・3名
(通所リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーションの内容)
第7条
事業所は利用者の状態に応じて次にあげるサービス提供を行うこととする。サービスは、1時間以上2時間未満の個別リハビリテーションとする。
①健康のチェック
②機能訓練
③送迎 (必要な場合のみ)
④リハビリテーション計画の作成
⑤評価・モニタリング
(通所リハビリテーションの計画)
第8条
1.通所リハビリテーション等の提供を開始する際には、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている状況を踏まえて、機能訓練の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した通所リハビリテーション計画を作成するものとする。なお、すでに居宅サービス計画が作成されている場合はその内容に沿った通所リハビリテーション計画を作成する。
2.通所リハビリテーション計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。
3.通所リハビリテーション計画を作成した際には、当該通所リハビリテーション計画を利用者に交付しなければならない。
4.それぞれの利用者について、通所リハビリテーション計画に従ったサービスの実施状況及び目標の達成状況の記録を行う。
(サービス提供の記録)
第9条
1.当事業所は、通所リハビリテーションを提供した際には、提供日及び提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに、利用者から申し出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければならない。
(通常の事業の実施地域)
第10条
通常の事業の実施地域(送迎ありの場合)は、事業所から3km圏内とする(当事業所から往復30分程度の範囲内)。3kmを越える送迎の希望がある場合は、当事業所が可否を判断する。
送迎なしの場合は、特に定めなし。
(利用料その他費用の額)
第11条
1.通所リハビリテーション等を提供した場合の利用者負担額は、介護保険法に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額とする。
2.第10条の通常の事業実施地域以外の地域に送迎を実施した場合の交通費については、次の額を徴収する。
(1)事業所から3km以上5km未満・・・1回の送迎につき200円
(2)事業所から5km以上6km未満・・・1回の送迎につき300円
※事業所から5km以上の地域は1km増すごとに+100円徴収する。
※原則として、事業所から5km圏外の場合は、送迎の対象とはならないが、必要な場合は相談の上、送迎の可否を判断する。その場合の交通費は上記のとおりとする。
3.前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名を受けることとする。
(虐待防止)
第12条
当事業所は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に挙げるとおり必要な措置を講じる。
1.虐待防止に関する責任者を選定する。
虐待防止に関する責任者・・・医師 佐久間研司
2.成年後見制度の利用を支援する。
3.苦情解決体制を整備する。
4.従業者に対する虐待防止を啓発・普及するために研修を実施する。
(身体拘束)
第13条
当事業所は、原則として利用者に対して身体拘束を行わない。ただし、自傷他害等のおそれがある場合など、利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことが考えられるときは、利用者に対して説明し、同意を得た上で、次に掲げることに留意して、必要最小限の範囲内で行うことがある。その場合は、身体拘束を行った日時、理由及び態様等についての記録を行う。
(1)緊急性・・・直ちに身体拘束を行わなければ、利用者本人または他人の生命・身体に危険が及ぶことが考えられる場合に限る。
(2)非代替性・・・身体拘束以外に、利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことを防止することができない場合に限る。
(3)一時性・・・利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことがなくなった場合は、直ちに身体拘束を解く。
(個人情報の保護及び守秘義務)
第14条
1.事業所が扱う個人情報の重要性を認識し、その適正な保護のために、自主的なルール及び体制を確立し、個人情報保護に関する法令その他の関係法令及び厚生労働省のガイドラインを遵守し、利用者の個人情報の保護を図る。
2.当事業所は、利用者に関する個人情報を「当院における利用者様の個人情報の利用目的について」に定める以外に利用しない。ただし、これらの目的以外に利用する必要が生じた際には、改めて利用者から同意を得る。
3.事業所の従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族等に関する秘密を、正当な理由なく第三者に漏らさない。
4.前項に掲げる事項は、利用終了後も同様の取り扱いとする。
(衛生管理等)
第15条
1.サービス提供職員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行う。
2.事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努める。
3.事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に挙げるとおり必要な措置を講じる。
(1)感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を開催し、その結果について従業者に周知徹底を図る。
(2)感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備する。
(3)従業者に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。
(非常災害対策)
第16条
1.事業所に災害対策に関する管理者を置き、非常災害に関する取り組みを行う。
非常災害に関する管理者・・・医師 佐久間研司
2.自然災害発生時における業務継続計画を作成し、従業者に内容の周知を図る。
3.従業者に対し、自然災害発生時の研修及び訓練を定期的に実施する。
(苦情処理)
第17条
1.当事業所は、通所リハビリテーション等の提供に対する利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、必要な措置を講じる。
2.当事業所は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録する。
3.提供した通所リハビリテーション等に関し、市町村が行う文書その他の物件の提出もしくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問もしくは照会に応じ、利用者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。
(緊急時等の対応)
第18条
従業者は、通所リハビリテーション等を提供中に、利用者に病状に急変が生じた場合やその他の必要な場合には、速やかに主治医に連絡を取るなど必要な措置を講じるとともに、当事業所の管理者に報告する。
(事故発生の防止及び発生時の対応)
第19条
当事業所は、安全かつ適切に質の高い介護・医療サービスを提供するために、事故発生の防止に努め、介護・医療事故を防止するための体制を整備する。
また、利用者に対する通所リハビリテーション等のサービス提供により事故が発生した場合は、速やかに利用者の家族、居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を行う。
(サービスの利用に当たっての留意事項)
第20条
1.利用者は、医師の診断や日常生活上の留意事項、利用当日の健康状態を職員に連絡し、心身の状況に応じたサービスの提供を受けるよう留意する。
2.通所リハビリテーション室の設備及び備品の利用は、本来の用法に従って利用し、誤った利用により破損が生じた場合には賠償を求めることがある。
3.医療機関での受診は、各家庭で行うものとする。
4.利用者の営利行為、宗教勧誘、特定の政治活動は禁止する。
5.他の利用者に対する迷惑行為は禁止する。
(その他運営に関する重要事項)
第21条
1.当事業所は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録並びに通所リハビリテーションの提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存する。また利用者もしくは連帯保証人の請求に応じて所定の手続きによりこれを開示し、又はその複写物を交付する。
(1)通所リハビリテーション計画
(2)提供した具体的なサービスの内容等の記録
(3)市町村への通知に係る記録
(4)苦情の内容等の記録
(5)事故の状況及び事故に際して行った処置についての記録
2.この規程に定める事項のほか、事業の運営に関する重要事項は、事業所の管理者及び通所リハビリテーション等の責任者との協議に基づき決定するものとする。
附則
この規程は、2017年10月1日から施行する。
この規程は、2019年1月1日から施行する。
この規程は、2020年1月6日から施行する。
この規程は、2020年2月21日から施行する。
この規程は、2023年6月5日から施行する。
この規程は、2023年9月29日から施行する。
この規程は、2024年12月27日から施行する。
この規程は、2025年6月6日から施行する。
通所リハビリテーション
介護予防通所リハビリテーション
(介護保険)
契約書
さくま内科・脳神経内科クリニック
通所リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーション契約書
利用者 様(以下、利用者)と、さくま内科・脳神経内科クリニック(以下、当事業者)は、通所リハビリテーションサービスの利用に関して、次のとおり契約を結ぶ。
第1条(目的)
1.当事業者は、介護保険法令の趣旨に従って、利用者がその有する能力に応じて可能な限り自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の心身の機能の維持回復を図ることを目的として、通所リハビリテーションサービスを提供する。
2.当事業者は、通所リハビリテーションサービスの提供にあたっては、利用者の要介護状態区分及び利用者の被保険者証に記載された認定審査会意見に従う。
第2条(契約期間)
1.契約期間は、西暦 年 月 日から西暦 年 月 日までとする。
但し、上記の契約期間の満了日前に、利用者が要介護区分の変更の認定を受け、要介護(支援)認定有効期間の満了日が更新された場合には、変更後の要介護(支援)認定有効期間の満了日までとする。
2.前項の契約期間の満了日の7日前までに利用者から更新拒絶の意思表示がない場合は、この契約は同一の内容で自動更新し、その後もこれに準じて更新する。
3.本契約が自動更新された場合、更新後の契約期間は、更新前の契約期間の満了日の翌日から更新後の要介護(支援)認定期間の満了日までとする。
第3条(運営規程の概要)
1.当事業者の運営規程の概要(事業の目的、職員の体制、通所リハビリテーションサービスの内容等)は、別紙重要事項説明書に記載したとおりとする。
第4条(通所リハビリテーション計画の作成・変更)
1.当事業者は、医師の診療に基づき、利用者の病状、心身の状況、日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、通所リハビリテーション計画を作成する。この計画には、通所リハビリテーションサービスの目標や目標達成のための具体的なサービス内容等を記載する。居宅サービス計画が作成されている場合は、その内容に沿って作成する。
2.当事業者は、次のいずれかに該当する場合には、第1条に規定する通所リハビリテーションサービスの目的に従い、通所リハビリテーション計画の変更を行う。
- 利用者の心身の状況、環境等の変化により、当該通所リハビリテーション計画を変更する必要がある場合。
- 利用者が通所リハビリテーションサービスの内容や提供方法等の変更を希望する場合。
3.当事業者は、通所リハビリテーション計画を作成し、又は変更した際には、これを利用者及び家族に対し説明し、その同意を得る。
第5条(通所リハビリテーションサービスの内容及びその提供)
1.当事業者は、第4条に定めた通所リハビリテーション計画に沿って、通所リハビリテーションを提供する。
第6条(サービス提供の記録)
1.当事業者は、利用者の通所リハビリテーションサービス提供に関する記録を作成し、その記録を利用終了後5年間は保管する。
2.当事業者は、利用者が記録の閲覧を求めた場合には、原則としてこれに応じる。但し、家族その他の者に対しては、利用者の承諾その他必要と認められる場合に限り、これに応じる。
第7条(居宅介護支援事業者等との連携)
1.当事業者は、利用者に対して通所リハビリテーションサービスを提供するに当たり、利用者が依頼する居宅介護支援事業者又はその他保険・医療・福祉サービスを提供する者との密接な連携を行う。
第8条(協力義務)
1.利用者は、当事業者が利用者のために通所リハビリテーションサービスを提供するに当たり、可能な限り当事業者に協力する。
第9条(サービス窓口)
1.当事業者は、苦情対応の責任者及びその連絡先を明らかにし、当事業者が提供した通所リハビリテーションサービスについて、利用者又は利用者の家族からの問い合わせがある場合は、迅速かつ誠実に必要な対応を行う。
第10条(緊急時の対応)
1.当事業者は、現に通所リハビリテーションサービスの提供を行っているときに利用者に容体の急変が生じた場合、速やかに主治医に連絡を取るなど必要な対応を講じる。
第11条(費用)
1.当事業者が提供する通所リハビリテーションサービスの利用単位毎の利用料その他の費用は、別紙重要事項説明書に記載したとおりとする。
2.利用者は、サービスの対価として、月ごとに算定された利用者負担額を当事業者に支払う。
3.当事業者は、通常の事業の実施地域以外にある利用者の居宅へ送迎を行う場合には、それに要した交通費の支払いを利用者に請求する。
4.当事業者は、通所リハビリテーションサービスの利用単位毎の利用料及びその他の費用の額を変更しようとする場合は、1か月前までに利用者に対し通知し、変更を申し出る。
第12条(利用者負担額の滞納)
1.利用者が正当な理由なく利用者負担額を2か月以上滞納し、催促したにもかかわらず30日以内に支払われない場合には契約を解除する。
第13条(秘密保持)
1.当事業者とその職員は、業務上知り得た利用者又は家族等に関する秘密を、正当な理由なく第三者に漏らさない。但し、次の各号についての情報提供については、利用者及び家族から予め同意を得た上で行う。
(1)介護保険サービス利用のための市町村、居宅介護支援事業者その他の介護保険事業者等への情報提供、あるいは、適切な居宅療養のための医療機関等への療養情報の提供。
2.当事業者は、利用者に関する個人情報を「当院における患者様の個人情報利用目的」に定める以外に利用しない。ただし、これらの目的以外に利用する必要が生じた際には、改めて利用者から同意を得る。
3.前項に掲げる事項は、利用終了後も同様の取り扱いとする。
第14条(虐待防止のための措置に関する事項)
1.当事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、以下の措置を講じる。
(1)虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催する。
(2)虐待防止のための指針を整備する。
(3)従業者に対して、虐待防止のための研修会を定期的に実施する。
(4)虐待防止の措置を講じるための担当者を配置する。
第15条(身体拘束)
1.当事業者は、利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下、身体的拘束等)は行わない。やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録するものとする。
第16条(感染症の予防及びまん延防止のための措置に関する事項)
1.当事業者は、感染症の予防及びまん延防止のため、以下の措置を講じる。
(1)感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催する。
(2)感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備する。
(3)従業者に対して、感染症の予防及びまん延防止のための研修会を定期的に実施する。
第17条(業務継続計画の策定等)
1.当事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する通所リハビリテーションサービスの提供を継続し、非常時の体制での早期の業務再開を図るための計画を策定し、当該業務計画に従い必要な措置を実施する。
2.当事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
第18条(利用者の解除権)
1.利用者は7日間以上の予告期間をもって、いつでもこの契約を解除することができる。
第19条(当事業者の解除権)
1.当事業者は、利用者が法令違反又はサービス提供を阻害する行為をなし、当事業者の再三の申し入れにもかかわらず、改善の見込みがなく、このサービス利用契約の目的を達することが困難になったときは、30日間以上の予告期間をもってこの契約を解除する。
第20条(契約の終了)
1.次に掲げるいずれかの事由が発生した場合は、この契約は終了する。
(1)利用者が要介護(支援)認定を受けられなかった場合。
(2)第2条1項及び2項により、契約期間満了日の7日前までに利用者から更新拒絶の申し出があり、かつ契約期間が満了した場合。
(3)利用者が第18条により契約を解除した場合。
(4)当事業者が第12条又は第19条により契約を解除した場合。
(5)利用者が介護保険施設や医療施設等へ入所または入院した場合。
(6)利用者が死亡した場合。
(7)その他、当事業者がサービス提供に不適と判断した場合。
第21条(損害賠償)
1.当事業者は、通所リハビリテーションサービスの提供にあたって、事故が発生した場合には、速やかに利用者の家族に連絡するとともに、必要な措置を講じる。
2.前項において、事故により利用者又はその家族の生命、身体、財産に損害が発生した場合は、当事業者は速やかにその損害を賠償する。ただし、当事業者に故意・過失がない場合はこの限りではない。
3.前項の場合において、当該事故発生につき利用者に重過失がある場合は、損害賠償の額を減額する。
4.次の各号に該当する場合は、当事業者は損害賠償責任を免れる。
(1)利用者が、利用者の心身の状況及び病歴の重要事項について故意にこれを告げず、又は不実告知を行ったことに専ら起因して損害が発生した場合。
(2)利用者が、サービス実施のための必要な事項に関する聴取・確認に対して、故意にこれを告げず、又は不実告知を行ったことに専ら起因して損害が発生した場合。
(3)利用者の急激な体調の変化等、当事業者が実施したサービスを原因としない事由に専ら起因して損害が発生した場合。
(4)利用者が、当事業者の指示・依頼に反して行った行為に起因して損害が発生した場合。
第22条(利用者の代理人)
1.利用者は、代理人を選任してこの契約を締結させることができ、また契約に定める権利の行使と義務の履行を代理して行わせることができる。
第23条(協議事項)
1.この契約に定めない事項については、介護保険法等の関係法令に従う。
(別紙)通所リハビリテーション重要事項説明書
通所リハビリテーションサービスの提供にあたり、当事業者が説明すべき重要事項は以下のとおりとします。
1.通所リハビリテーションサービスを提供する事業者(法人)について
|
法人の名称 |
医療法人 聡智会 |
|
代表者名 |
院長 佐久間 研司 |
|
所在地・連絡先 |
住所:鳥取県米子市長砂町59-1 電話:0859-30-2000 FAX:0859-30-2001 |
2.サービス提供を実施する事業所の概要
(1)事業所名称及び事業所番号
|
事業所名 |
さくま内科・脳神経内科クリニック |
|
所在地・連絡先 |
住所:鳥取県米子市長砂町59-1 電話:0859-30-2000 FAX:0859-30-2001 |
|
介護保険事業者番号 |
3110213521 |
|
管理者名 |
院長 佐久間 研司 |
(2)事業の目的及び運営の方針
|
事業の目的 |
医療法人聡智会が開設するさくま内科・脳神経内科クリニック(以下「事業所」という)が行う、指定通所リハビリテーション及び指定介護予防通所リハビリテーション(以下「通所リハビリテーション等」という)の適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の従業者が、計画的な医学的管理を行っている医師の指示に基づき、要介護状態(介護予防通所リハビリテーションにあたっては要支援状態)と認定された利用者(以下「利用者」という)に対し、介護保険法の趣旨に従って通所リハビリテーション等を提供することを目的とする。 |
|
運営の方針 |
①事業所の従業者は、利用者が、居宅においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、理学療法及びその他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能維持向上を図るものとする。 ②通所リハビリテーション等の実施に当たっては、利用者の要介護状態の軽減もしくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するようその目的を設定し、その目的に沿ったリハビリテーションを計画的に行う。 ③通所リハビリテーション等の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、居宅介護支援事業所、地域の保健・医療・福祉サービスとの密接な連携を図り、利用者が地域において総合的サービス提供を受けることができるよう努めるものとする。 ④サービス提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又は家族に対して療養上必要な事項について理解しやすいように指導又は説明を行うとともに、利用者の同意を得て実施するよう努めるものとする。 |
(3)営業日及び営業時間
|
月曜日~土曜日 |
月曜~金曜 9時00分~19時00分 土曜(午前)9時00分~12時00分 |
|
休日 |
土曜(午後)、日曜、祝日、年ごとに定める盆休み、年末年始 |
(4)サービス提供時間と1単位あたりの利用定員
|
月曜日~金曜日 (水曜の午前は 提供なし) |
①9時00分~10時05分 ②10時30分~11時35分 ③16時10分~17時15分 |
|
土曜日 |
①9時00分~10時05分 ②10時30分~11時35分 |
|
利用定員 |
3人 |
(5)事業所の職員体制
|
|
常 勤 |
非常勤 |
|
|
医師 |
1人 |
|
通所リハビリテーション等を実施するにあたり、リハビリテーション計画の作成に係る診療を実施 |
|
理学療法士 |
2人 |
1人 |
通所リハビリテーション等の提供にあたる |
|
作業療法士 |
0人 |
|
|
|
言語聴覚士 |
0人 |
|
|
(6)事業の実施地域
|
通常実施地域 (送迎ありの場合) |
事業所から3km圏内(当事業所から往復30分程度の範囲内) |
|
送迎なしの場合 |
定めなし |
※事業所から3km圏外にお住まいの方で送迎が必要な場合は、別途交通費を頂きます。
3.提供するサービスの内容及び費用について
(1)提供するサービス内容
|
サービス区分と種類 |
サービス内容 |
|
1時間以上2時間未満の 指定通所リハビリテーション (指定介護予防通所リハビリ テーション) |
医師の指示のもと、理学療法士が利用者様の日常生活がより活動的なものとなるように、通所リハビリテーション計画に沿って、1時間以上2時間未満の個別リハビリテーションを提供する。 具体的な訓練内容は以下のとおりとする。 ①運動療法(関節可動域練習、筋力強化練習、歩行練習、日常生活動作(ADL)に関する練習等) ②ニューステップ等の機器を用いた訓練 ③物理療法(ホットパック、干渉波) ④自主トレーニング指導(各個人に合わせて自宅で行える運動を立案) |
(2)通所リハビリテーション利用料(1時間以上2時間未満、1単位=10.00円)
|
要介護の場合(1日につき) |
|||
|
項目 |
単位 |
単価 |
利用者負担 (1割の場合) |
|
要介護1 |
369単位/日 |
3690円/日 |
369円/日 |
|
要介護2 |
398単位/日 |
3980円/日 |
398円/日 |
|
要介護3 |
429単位/日 |
4290円/日 |
429円/日 |
|
要介護4 |
458単位/日 |
4580円/日 |
458円/日 |
|
要介護5 |
491単位/日 |
4910円/日 |
491円/日 |
|
短期集中個別リハビリ テーション実施加算 (退院・退所・認定日より 3ヵ月以内) |
110単位/日 |
1100円/日 |
110円/日 |
|
サービス提供体制強化加算Ⅲ |
6単位/日 |
60円/日 |
6円/日 |
|
退院時共同指導加算 (退院につき1回まで) |
600単位/回 |
6000円 |
600円 |
|
送迎を行わなかった場合の減算 |
-47単位/片道 |
-470円/片道 |
-47円/片道 |
|
要支援の場合(1月につき) |
|||
|
項目 |
単位 |
単価 |
利用者負担 (1割の場合) |
|
要支援1 |
2268単位/月 |
22680円/月 |
2268円/月 |
|
要支援2 |
4228単位/月 |
42280円/月 |
4228円/月 |
|
サービス提供体制強化加算Ⅲ |
24単位/月 または 48単位/月 |
240円/月 または 480円/月 |
24円/月 または 48円/月 |
|
退院時共同指導加算 (退院につき1回まで) |
600単位/回 |
6000円 |
600円 |
|
利用開始日に属する月から 12ヵ月超 |
-120単位/月または -240単位/月 |
-1200円/月または -2400円/月 |
-120円/月 または -240円/月 |
※上記は、要介護者は1日あたりの利用料、要支援者は1ヵ月あたりの利用料となっています。
※短期集中個別リハビリテーション実施加算は、退院後又は認定日より3ヵ月以内でかつ週2回以上の場合に加算します。(要介護のみ)
※サービス提供体制強化加算Ⅲは、勤続年数7年以上の理学療法士が在籍する事業所において算定できる加算です。
※退院時共同指導加算は、入院中の者が退院するにあたり、通所リハビリテーション事業所の医師又は理学療法士が退院前カンファレンスに参加し、退院時共同指導を行った後に、当該者に対する初回の通所リハビリテーションを行った場合に、当該退院につき1回に限り加算します。
※介護予防通所リハビリテーション(要支援)では、利用開始から12ヵ月を超える場合は、要支援1では120単位/月の減算、要支援2では240単位/月の減算になります。
※介護保険での給付の範囲を超えたサービスの利用料金は、全額が利用者の自己負担となりますのでご相談ください。
(3)交通費
2の(6)の事業実施地域(送迎ありの場合)以外にお住まいの方は交通費が必要となります。
|
事業所から3km以上5km未満 |
1回の送迎につき200円 |
|
事業所から5km以上6km未満 |
1回の送迎につき300円 |
※事業所から5km以上の地域は1km増すごとに+100円徴収します。
※原則として、事業所から5km圏外にお住まいの方に対する送迎は行っておりません。送迎が必要な場合には、相談の上、送迎の可否を決定いたします。送迎を行う場合の交通費は、上記記載のとおりです。
(4)その他の費用
サービス実施に必要な居宅の水道・ガス・電気・電話等の費用は、利用者負担となります。
(5)利用料等のお支払い方法
利用月の月末で締め、翌月の利用時に前月分をまとめてお支払いいただくようになります。
金額については、事前にお知らせいたします。
4.サービスの提供にあたって
(1)サービスの提供に先立って、介護保険被保険者証に記載された内容(被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間)を確認させていただきます。被保険者の住所などに変更があった場合は速やかに当事業者にお知らせください。
(2)利用者が要介護認定を受けていない場合には、利用者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行います。また、居宅介護支援が利用者に対して行われていない等の場合であって、必要と認められるときは、要介護認定の更新の申請が遅くとも利用者が受けている要介護認定の有効期間が終了する30日前にはなされるよう、必要な援助を行うものとします。
(3)医師及び理学療法士は、医師の診療に基づき、利用者の病状、心身の状況、日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、通所リハビリテーション計画を作成します。居宅サービス計画が作成されている場合は、その内容に沿って作成します。作成した計画について、利用者又は家族に説明し、同意を得た上で、利用者に交付します。計画に従ったサービスの実施状況及びその評価について、速やかに診療記録を作成するとともに、医師に報告します。
5.個人情報の保護と秘密の保持について
(1)当事業者は、利用者又はその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」を遵守し、適切な取り扱いに努めるものとします。
(2)当事業者が得た利用者又はその家族の個人情報については、サービス提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又はその家族の同意を得るものとします。
(3)当事業者及び従業者は、サービス提供をする上で知り得た利用者又はその家族の秘密を正当な理由なく第三者に漏らしません。この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了した後も継続します。
6.虐待防止について
当事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。
(1)虐待防止に関する責任者を選定しています。(虐待防止に関する責任者:佐久間研司)
(2)虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催しています。
(3)虐待防止のための指針の整備をしています。
(4)従業者に対して虐待を防止するための研修会を定期的に実施しています。
7.身体拘束について
(1)利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束を行いません。
(2)身体的拘束を行う場合には、利用者又は利用者の家族に同意を得るとともに、態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録します。
8.衛生管理等について
(1)サービス提供職員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います。
(2)事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めます。
(3)当事業者は、感染症が発生し又はまん延しないように、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。
・感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催しています。
・感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備しています。
・従業者に対して感染症の予防及びまん延防止のための研修会を定期的に実施しています。
9.業務継続計画の策定等について
(1)感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する通所リハビリテーションの提供を継続し、非常時の体制での早期の業務再開を図るための計画を策定し、当該業務継続計画に従って必要な措置を講じます。
(2)従業者に対して、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施します。
(3)定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。
10.自然災害時の対応について
地震や台風、大雪などの災害によって送迎が困難である場合や連絡がつきにくい状況等の場合においては、急遽サービスを中止させていただく場合があります。予めご了承ください。その後の対応につきましては、連絡がつき次第従業者を通して安否確認を行い今後のサービス再開について説明を行います。サービス復旧の目処が立った段階でサービスの再開を行いますが、長期間にわたり復旧が困難であると判断した場合には、他事業所への紹介を行う場合があります。
11.キャンセルについて
利用者がサービスの利用をキャンセルする際には、速やかに当事業所までご連絡ください。
12.サービス提供に関する相談、苦情についての窓口
提供した通所リハビリテーションに係る利用者及びその家族からの相談及び苦情を受け付けるための窓口を設置します。
|
窓口責任者 |
佐久間 研司 |
|
連絡先 |
電話:0859-30-2000(9時00分~19時00分) |
13.緊急時及び事故発生時の対応方法について
従業者は、通所リハビリテーション等の提供中に利用者の病状に急変が生じた場合等には、速やかに主治医に連絡を取るなど必要な措置を講じるとともに、当事業所の管理者に報告します。
また、通所リハビリテーション等の提供により事故が発生した場合は、利用者の家族、当事業所の管理者、利用者に関わる居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。
|
主 治 医 |
病 院 名 及び 所 在 地 |
|
|
氏 名 |
|
|
|
電話番号 |
|
|
|
緊急連絡先 (家族等) |
氏名(続柄) |
|
|
住 所 |
|
|
|
電話番号 |
|
14.重要事項説明の年月日
|
重要事項説明の年月日 |
西暦 年 月 日 |
通所リハビリテーションを実施するにあたり、利用者に対して、契約書及び重要事項説明書に基づいて重要な事項を説明しました。
|
所在地 |
鳥取県米子市長砂町59-1 |
|
事業者 |
さくま内科・脳神経内科クリニック 印 |
|
説明者 |
氏名 印 |
私は、契約書及び重要事項説明書に基づいて、通所リハビリテーションについての重要事項の説明を受け、通所リハビリテーションをさくま内科・脳神経内科クリニックにて受けることに同意します。
|
利用者 |
住所 |
|
|
氏名 |
印 |
|
|
代理人 |
住所 |
|
|
氏名 |
印 |
個人情報に関する同意書
さくま内科・脳神経内科クリニック 様
通所リハビリテーションサービス実施に必要な、私または家族の個人情報を、さくま内科・脳神経内科クリニックが必要最低限の範囲内で使用、提供、または収集することに同意します。
西暦 年 月 日
利用者 氏名 印
代理人 氏名 印
交通費に関する同意書
さくま内科・脳神経内科クリニック 様
通常の事業実施地域(送迎ありの場合)を越えて、送迎つきの通所リハビリテーションサービスを利用するにあたり、
事業所からの距離が kmのため、1回の送迎につき 円の交通費を支払うことに同意します。
西暦 年 月 日
利用者 氏名 印
代理人 氏名 印